「自己分析って、どうやって始めればいいんだろう…」
「何を考えればいいのかわからない…」
こんな疑問を解決します。
自己分析には、いくつかの体系的なアプローチ方法が確立されています。
自分史作成、モチベーショングラフ、マインドマップなど、様々なツールを組み合わせることで、自分自身の価値観や強み、可能性を明確に見出すことができます。
「でも、本当にそれで自分のことがわかるの?」
と疑問に思う方もいるでしょう。
しかし、ご安心ください。これらの方法は、多くの就活生や転職者が実際に成果を上げてきた実践的な手法です。私自身も実践してきました。
この記事では、各手法の具体的な実施方法から活用のコツまで、現役キャリアコンサルタントの視点で徹底的に解説していきます。
- 就職活動や転職を控えている方
- 自分の強みや適性を知りたい方
- キャリアの方向性を定めたい方
- 自己理解を深めたい方
ぜひ最後までお読みいただき、効果的な自己分析の第一歩を踏み出してください。
自己分析の基本的なやり方

自己分析は、就職活動や転職、キャリアプランニングにおいて非常に重要な役割を果たします。
自分自身の価値観、強み、興味関心を深く理解することで、より明確な将来の方向性を見出すことができます。
以下では、効果的な自己分析の主要な方法とそれぞれの特徴について詳しく解説していきます。
これらの手法を組み合わせることで、より包括的な自己理解が可能になります。
自分史の作成
自分史の作成は、過去の経験や出来事を時系列で整理し、自己理解を深めるための重要なツールです。
自分史は以下のようなものです。
| 年齢 | 印象的な出来事 | 感じた、考えたこと | 価値観、強み弱み、興味 |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 学級委員長に推薦される。 | 嫌がる人が多かったけど、嫌いじゃなかった | リーダーシップ |
| 12歳 | バスケ部キャプテンになる。 | 強くはなかったけど、後輩とも仲良くできた | 年下とのコミュニケーション |
| 15歳 | クラスで不登校の子に配布物を持って行った。 | 少し責任を感じていた | 責任感 |
| 18歳 | 高卒で建設会社へ就職 | 社会人になることが嬉しかった | 自立 |
| 21歳 | 退職 | 同じことの繰り返しがつまらないと感じた。今考えると残業も多かった。 | 同じ作業の繰り返しは苦手、メリハリ、好奇心 |
| 21歳 | IT系の専門学校に入学 | これからの時代はパソコンだと思った | パソコン |
| 24歳 | ホームページ作成会社に就職 | 先輩や上司も良いい人だった。積極的に話すようになった。 | 人間関係 |
| 27歳 | 主任に昇格 | 新人教育でプログラムを考えたり、新人の悩みを聞くのが楽しかった | 悩みを聞く |
この方法が効果的な理由は、人生の重要な出来事や転機を振り返ることで、自分の価値観や行動パターンの形成過程を明確に理解できるからです。
例えば、学生時代の部活動での成功体験、アルバイトでの失敗、進路選択の際の決断など、様々な経験を時系列で整理することで、自分がどのように成長し、現在の価値観が形成されてきたのかが見えてきます。
特に就職活動では、自己PRや志望動機を作成する際の重要な材料となります。
このように、自分史の作成は自己分析の基礎となる重要なステップといえます。
自分史の具体的な作成方法やポイントについては、別記事「自分史の書き方!例文あり!徹底解説!」で詳しく解説しています。
「私は自分史を作成する過程で、困難を乗り越えた経験が自分の強みの形成に大きく影響していることに気づきました」
モチベーショングラフの作成
モチベーショングラフは、過去から現在までの自分のやる気の変化を可視化するツールです。
モチベーショングラフは以下のようなものです。

このグラフを作成することで、自分の転機や価値観の変化を明確に把握することができます。
時系列で自分の感情の起伏を振り返ることで、どのような経験や出来事が自分に大きな影響を与えたのかが見えてくるのです。
例えば、学生時代のクラブ活動での成功体験や、アルバイトでの挫折など、人生の重要な出来事とその時の感情を縦軸(モチベーション度)と横軸(時間)にプロットしていくことで、自分の価値観や行動パターンが明確になっていきます。
このように、モチベーショングラフは自己分析において非常に効果的なツールといえます。
モチベーショングラフの具体的な作り方や活用方法については、別記事「モチベーショングラフの書き方、使い方を徹底解説!」で詳しく解説しています。
「私自身、モチベーショングラフを作成して初めて、自分が『人との関わり』に強くモチベーションを感じるタイプだと気づきました」
マインドマップの作成
マインドマップは、アイデアや考えを視覚的に整理するための強力なツールです。

脳の自然な思考プロセスに沿って情報を放射状に広げていくことで、自分の興味や能力、価値観などを体系的に整理できます。
例えば、中心に「私」という単語を置き、そこから「趣味」「仕事」「性格」などのカテゴリーを枝分かれさせ、さらにそこから具体的な要素を書き出していくことで、自分に関する様々な側面を可視化することができます。
これにより、今まで気づかなかった自分の特徴や傾向が浮かび上がってきます。
このように、マインドマップは自己理解を深めるための効果的な手法といえます。
マインドマップは手書きでやる方法のほかに様々なデジタルツールで使用も可能です。
マインドマップの具体的な作成方法や活用例については、別記事「マインドマップで自己分析するやり方を徹底解説!」で詳しく解説しています。
「私は、マインドマップを作成することで、自分の興味の方向性が『創造的な問題解決』に集中していることに気づくことができました」
「なぜ?」の深掘り
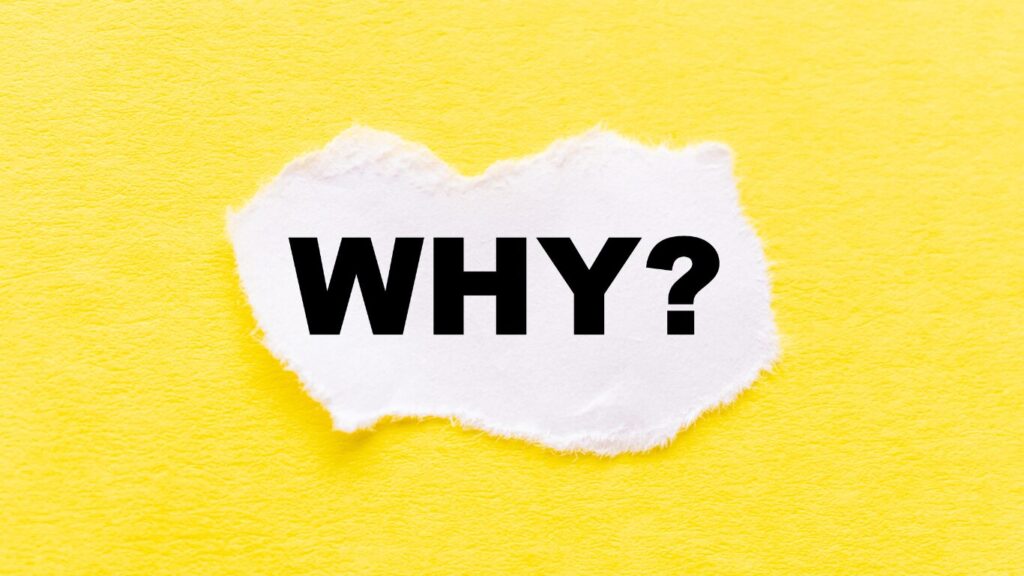
もともとは問題の根本原因を考える手法です。
そのため医療介護分野では、事故分析等で使用されることが多いです。
それを自己分析で応用する方法です。
「なぜ?」を繰り返し問いかけることで、自分の本質的な価値観や動機を明らかにすることができます。
「自分の本当の価値観や動機を知るためには、最初の答えに満足せず、『なぜ?』を繰り返し問いかけることが大切です。この過程は時間がかかりますが、必ず自己理解の深まりにつながります」
「なぜ?」の深堀が効果的な理由
この手法が効果的な理由は、表面的な答えから徐々に掘り下げていくことで、自分でも気づいていなかった深層的な考えや感情に到達できるからです。
また、この過程で自分の決断や行動の真の理由を理解することができます。
例えば、「なぜ営業職に興味があるのか?」という質問に対して、「人と接することが好きだから」という最初の答えから、さらに「なぜ人と接することが好きなのか?」と掘り下げていくことで、「相手の課題を解決できたときの達成感が好きだから」「他者との関わりを通じて自分も成長できるから」といった、より本質的な理由が見えてきます。
「自分の中にある、気持ちや価値観を言語化するのにオススメです。」
「なぜ?」の深堀、「5why」
「5why」というやり方があります。
これはトヨタ自動車株式会社も取り入れている方法になります。
「5why(Five whys)」とは? 「5why」は、問題解決する際に「原因と結果との関係を明らかにする」使う手法です。 つまり、基準と現状とのギャップの要因(原因)を明確にする手法です。
この「5why」は、「なぜ?」を5回問うことにより、様様な要因のうちから真因を見極めるための手法です。
もっと噛み砕いていえば、問題が起きた時に「なぜ問題が起きたのか?」と掘り下げて問うことです。
「興味のある方は、トヨタの元副社長の大野耐一氏の著書「トヨタ生産方式」を是非一読されてみてくださいね。」
「なぜ?」の深堀りのメリット
- 本質的な自己理解が深まる。表面的な理由から真の動機まで掘り下げることができます。
- blind spotの発見。自分でも気づいていなかった価値観や考え方に気づくことができます。
- 「なぜ?」への回答を準備することで、面接での質問に的確に答えられます。
- 他の自己分析に比べ短時間で実施することが可能。
「なぜ?」の深堀りのデメリット
- 時間がかかる。一つの質問に対して深く考える必要があり、時間を要します。
- 心理的負担。自分の内面と向き合うため、精神的なストレスを感じることがあります。
- 行き詰まりのリスク。あまりに深く考えすぎると、答えが見つからなくなることがあります。
「なぜ?」の深堀のやり方
「なぜ?」の深堀りを行う際は、以下のステップを意識すると効果的です。
- まず、分析したいテーマについて具体的な質問を設定する
- その答えに対してさらに「なぜ?」と問いかけ、より深い理由を探る
- この過程を最低5回繰り返し、本質的な理由にたどり着くまで続ける
「なぜ?」深掘りの例
具体例として、以下のような深掘りの例が考えられます。
Q1: なぜプログラミングを学びたいのか? A1: 「新しいアプリを作りたいから」
Q2: なぜ新しいアプリを作りたいのか? A2: 「人々の生活を便利にしたいから」
Q3: なぜ人々の生活を便利にしたいのか? A3: 「技術で社会に貢献したいから」
Q4: なぜ技術で社会に貢献したいのか? A4: 「自分のスキルを活かして人の役に立ちたいから」
Q5: なぜ人の役に立ちたいのか? A5: 「他者の成長や成功を支援することに喜びを感じるから」
このように、表面的な理由から徐々に本質的な価値観や動機を明らかにしていくことができます。
「私は『なぜ?』を5回繰り返すことで、自分の行動の根底にある『人の精神的成長を支援したい』という価値観を発見することができました」
他己分析の活用
他己分析とは、周囲の人からフィードバックをもらい、客観的な視点で自分を理解する方法です。
この手法が重要な理由は、自分では気づかない特徴や長所、改善点を発見できるからです。
また、他者からの評価は就職活動や career 選択において貴重な参考情報となります。
例えば、友人や先輩、家族など異なる立場の人々から「あなたの強みは何だと思うか」「どんな場面で活躍していると感じるか」といった質問を投げかけ、多角的な視点で自己理解を深めることができます。
特に、学生時代のグループワークでのリーダー経験や、アルバイトでの接客評価など、具体的なフィードバックは自己PR作成に活用できます。
このように、他己分析は自己分析を補完し、より客観的で信頼性の高い自己理解を可能にする重要なツールです。
他己分析の具体的な実施方法や活用のポイントについては、別記事「他己分析のやり方を徹底解説!」で詳しく解説しています。
「私は他己分析を通じて、自分が思っている以上にチームワークを重視するタイプだということに気づくことができました」
ジョハリの窓の利用
ジョハリの窓は、自己理解と他者からの認識のギャップを分析するための効果的なツールです。
この手法が重要なのは、「開放の窓」「盲点の窓」「秘密の窓」「未知の窓」という4つの領域から、自己認識と他者認識の関係性を体系的に理解できるからです。
ジョハリの窓は以下のようなフレームワークを言います。

例えば、自分では気づいていない長所(盲点の窓)を発見したり、自分では隠しているつもりの特徴が他者には明らかに見えている(秘密の窓)といった気づきを得ることができます。
就職活動では、この分析結果を面接での自己PRや、職業選択の判断材料として活用できます。
このように、ジョハリの窓は自己分析において、客観的な視点を取り入れるための重要なフレームワークとなります。
ジョハリの窓の詳細な活用方法や実践的なワークシートについては、別記事「ジョハリの窓のやり方とは?自己分析の仕方を徹底解説!」で解説しています。
「「私はジョハリの窓分析を通じて、自分の『謙虚さ』が他者からは『自信のなさ』として映っていることに気づき、コミュニケーションスタイルを改善することができました」
Wll・Can・Mustフレームの活用
Will・Can・Mustフレームは、自己分析において自分の意志・能力・義務を明確に区分けするための効果的なツールです。
このフレームワークが重要な理由は、「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「しなければならないこと(Must)」という3つの視点から自分を分析することで、より現実的なキャリアプランを立てることができるからです。

例えば、「プログラミング(Can)」のスキルを活かしながら、「社会貢献(Will)」という願望を実現し、「収入の安定(Must)」を確保するといった形で、具体的な職業選択や目標設定に活用できます。
また、これらの要素の重なり具合を見ることで、自分にとって理想的な仕事や役割が見えてきます。
このように、Will・Can・Mustフレームは、バランスの取れたキャリア選択を支援する実践的なツールとして有効です。
Will・Can・Mustフレームの具体的な活用方法や分析手順については、別記事「自分に向いている職業とは?考え方と探す方法を徹底解説!」で詳しく解説しています。
「Will・Can・Mustは、「仕事を辞めたい理由」を考えるのにも有効です。」
自己分析の効果的なやり方
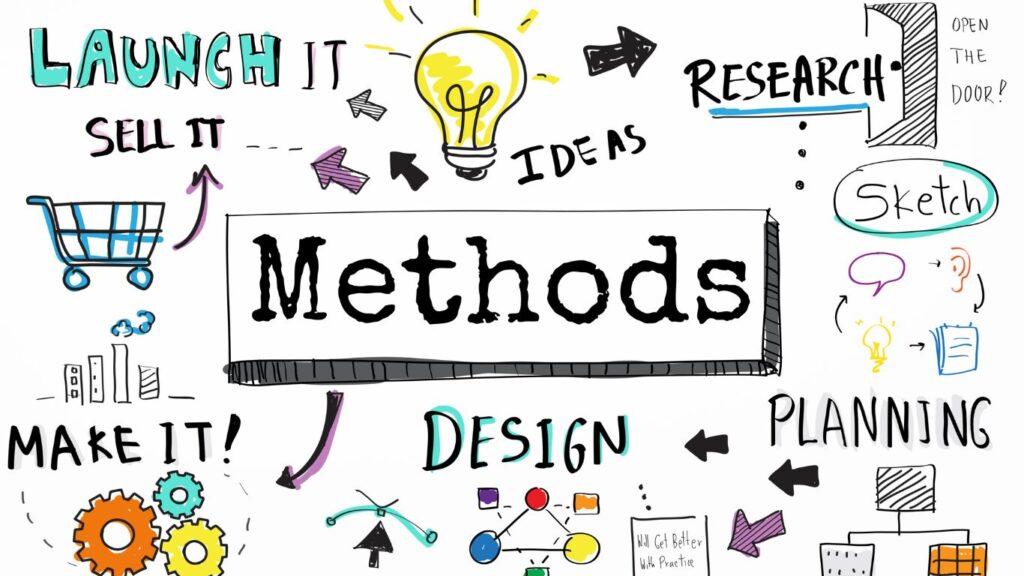
自己分析を効果的に行うためには、以下のようなポイントに注意を払うことが重要です。
これらのポイントを意識することで、より深い自己理解と具体的な成長につながる分析が可能となります。
短所などネガティブな部分も考える
自己分析では、短所やネガティブな面も正直に見つめ直すことが重要です。
なぜなら、自分の弱みや改善点を理解することで、より効果的な成長戦略を立てることができ、また面接での質問にも適切に対応できるようになるからです。
例えば、「期限に追われると焦ってしまう」という短所を認識した場合、それを「だからこそスケジュール管理を徹底し、余裕を持って行動するよう心がけている」というように、改善のための具体的な行動に結びつけることができます。
就職活動では、このような短所への対処法を説明できることが、むしろ強みとなります。
このように、短所を含めた総合的な自己理解は、より実践的で信頼性の高い自己分析につながります。
短所の分析方法や効果的な改善策については、別記事「短所を強みに変える自己分析テクニック」で詳しく解説しています。
「短所と長所の本質は同じもので、環境によって長所や短所になるのです。」
主観と客観を分ける
自己分析では、主観的な認識と客観的な事実を明確に区別することが重要です。
この区別が重要な理由は、自分の感情や思い込みに左右されない、より正確な自己理解を得ることができるからです。
また、就職活動における面接や自己PRでも、具体的な事実に基づいた説明の方が説得力があります。
例えば、「私はリーダーシップがある」という主観的な認識に対して、「学園祭の実行委員長として30人のチームを統括し、過去最高の来場者数を達成した」という客観的な事実を区別して整理することで、より具体的で説得力のある自己アピールが可能になります。
就職活動では、このような事実に基づいたエピソードを準備することが重要です。
このように、主観と客観を分けて考えることは、より信頼性の高い自己分析と効果的な自己アピールにつながります。
「主観と客観を分けて考えることは、仕事でのコミュニケーションにも活きてきますね。」
考えた過程もメモする
自己分析では、考えた過程や思考の流れをメモすることが重要です。
なぜなら、後で振り返った時に、その時の判断基準や価値観の変化を追跡できるだけでなく、面接での質問に対してより深い洞察を持って回答できるようになるからです。
例えば、「なぜその部活動を選んだのか」という質問に対して、「単に野球が好きだったから」という表面的な回答ではなく、「チームスポーツを通じて協調性を養いたいと考え、その中でも戦略性の高い野球を選択した」というように、当時の思考プロセスを説明できるようになります。
就職活動では、このような深い自己理解と論理的な説明が高く評価されます。
このように、考えた過程をメモすることは、より深い自己理解と効果的な自己アピールにつながります。
「私は思考プロセスをメモすることで、自分の意思決定パターンが見えてきて、より効率的な判断ができるようになりました」
周囲の人に深掘りしてもらう
自己分析では、周囲の人からのフィードバックを積極的に求めることが重要です。
なぜなら、自分では気づかない特徴や長所、改善点を客観的な視点から発見できるだけでなく、より多角的な自己理解が可能になるからです。
また、就職活動における自己PRや面接でも、他者からの具体的なフィードバックに基づいた説明の方が説得力があります。
例えば、「自分は協調性があると思う」という自己認識に対して、「グループプロジェクトで意見が対立した際に、メンバーの意見を丁寧に聞き、建設的な解決策を提案していた」という具体的なフィードバックを得ることで、より具体的で説得力のある自己アピールが可能になります。
就職活動では、このような第三者からの具体的な評価を活用することが有効です。
このように、周囲の人からのフィードバックを求めることは、より客観的で深い自己理解につながります。
「主観だけでなく、客観的な視点を取り入れることは自己分析において重要です。」
自己分析をするときの注意点
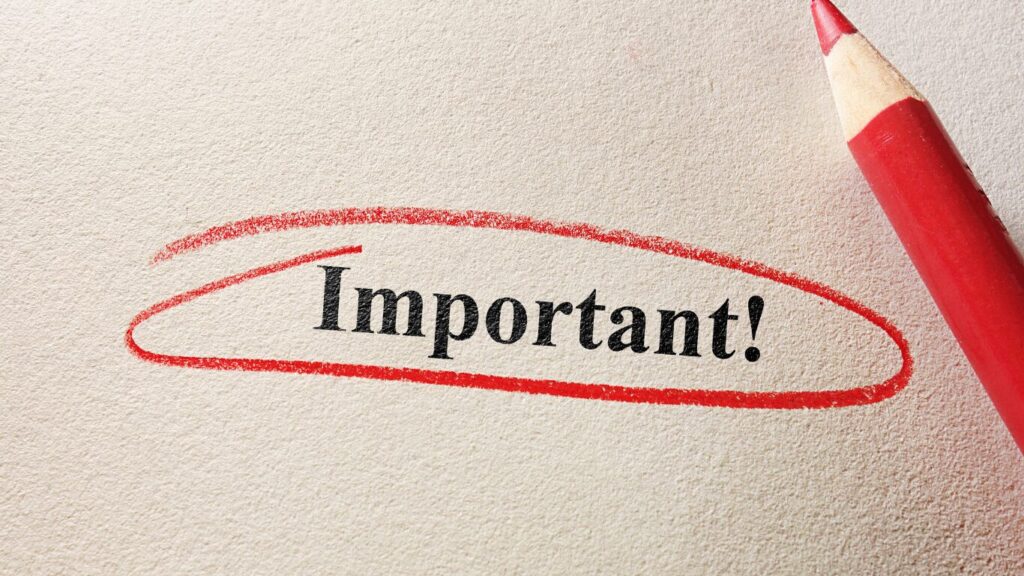
自己分析をする際には、以下の注意点を意識することで、より効果的な分析が可能になります。
これらの点に気をつけることで、就職活動やキャリア選択において、より確かな判断材料を得ることができます。
思い込みで決めない
自己分析において、思い込みで結論を出すことは避けるべきです。
なぜなら、先入観や固定観念に基づいた判断は、自分の本当の特徴や可能性を見誤る原因となり、キャリア選択に悪影響を及ぼす可能性があるからです。
例えば、「私は人前で話すのが苦手だから営業職は向いていない」と思い込んでしまうケースがありますが、実際には苦手意識を克服するための努力や、営業職に必要な他のスキル(傾聴力や問題解決能力など)を持っている可能性があります。
就職活動では、このような思い込みによる自己制限を避け、より広い視野で自己分析を行うことが重要です。
このように、客観的な事実や経験に基づいて自己分析を行うことで、より正確な自己理解と可能性の発見につながります。
「思い込みは意識していないことも多いです。注意しましょう。」
嘘の出来事や経験を作らない
自己分析において、虚偽の経験や実績を作り上げることは絶対に避けるべきです。
なぜなら、嘘の情報は面接などで容易に見破られる可能性が高く、信頼を大きく損なうことになるだけでなく、正確な自己理解を妨げることにもなるからです。
例えば、「実際には経験していない海外留学の体験を作り上げる」「存在しないボランティア活動の実績を記載する」といった行為は、面接での詳細な質問に答えられず、企業からの信用を完全に失うことになります。
就職活動では、たとえ小さな成果でも、実際の経験に基づいた誠実な自己アピールの方が高く評価されます。
このように、自己分析では常に事実に基づいた正直な振り返りを心がけることが重要です。
「正直に向き合えば、必ず自分らしさが見えてきます」
企業の求める人物像に寄せない
自己分析において、企業の求める人物像に合わせようとすることは避けるべきです。
なぜなら、企業の求める人物像に無理に合わせることは、自分の本質的な価値観や強みを見失うことにつながり、長期的なキャリア形成において問題を引き起こす可能性があるからです。
例えば、「この業界では体育会系の人材が求められている」という先入観から、自分の性格や価値観に反して強引な自己アピールをしてしまうケースがあります。
しかし、このような不自然な自己表現は面接で容易に見破られ、かえって評価を下げることになります。
就職活動では、企業の求める人物像を理解しつつも、自分の本質的な強みや価値観に基づいた誠実な自己アピールの方が、結果として良い結果につながります。
このように、自己分析では自分の本質を見つめ直し、ありのままの自分を理解することが重要です。
「自分らしさを失わない自己分析が、最も説得力のある自己アピールにつながります」
自己分析だけに時間を割きすぎない
自己分析に過度な時間を費やすことは、就職活動全体のバランスを崩す原因となるため、適切な時間配分が重要です。
なぜなら、自己分析は就職活動における重要な要素の一つですが、業界研究、企業研究、面接対策など、他にも取り組むべき重要な活動が多くあるからです。
例えば、「完璧な自己分析をしてから企業研究を始めよう」と考えて3ヶ月以上自己分析に費やし、結果として企業研究や面接対策の時間が不足してしまうケースがあります。
就職活動では、各活動にバランスよく時間を配分し、並行して進めることが効果的です。
このように、自己分析は重要ですが、適切な時間配分を意識して進めることが成功への鍵となります。
「自己分析は完璧を目指すのではなく、継続的に深めていくものです」
自己分析するメリット

自己分析には、就職活動やキャリア形成において、様々なメリットがあります。
ここでは、主要な3つのメリットについて詳しく解説していきます。
自分の価値観を知れる
自己分析を通じて、自分自身の本質的な価値観を明確に理解することができます。
なぜなら、日常生活や過去の経験を深く掘り下げて分析することで、自分が何を大切にし、何に喜びを感じ、何を重視して決断を下してきたのかが見えてくるからです。
例えば、
- 「なぜその部活動を選んだのか」
- 「どんな時にやりがいを感じるのか」
- 「困難な状況でどのような選択をしたのか」
といった具体的な経験を分析することで、
- 「チームワークを重視する価値観」
- 「創造性を大切にする姿勢」
- 「挑戦を恐れない性格」
といった自分の根本的な価値観が浮かび上がってきます。
就職活動では、この価値観の理解が企業選びの重要な判断基準となります。
このように、価値観の明確化は、より自分らしいキャリア選択への第一歩となります。
価値観の発見方法や分析手法について、このブログでは価値観の基礎知識、価値観の見つけ方、価値観の活かし方というカテゴリーで解説しています。是非ブログ内の記事をみてみてくださいね。
「価値観は人生の羅針盤です。しっかりと向き合いましょう」
自己PRや志望動機の作成に役立つ
自己分析は、効果的な自己PRや説得力のある志望動機を作成する上で非常に重要な役割を果たします。
なぜなら、自己分析を通じて得られた具体的なエピソードや経験は、自分の強みや成長過程を裏付ける強力な証拠となり、面接官に対して説得力のある説明を可能にするからです。
例えば、「なぜその経験が自分の強みになったのか」「その経験を通じて何を学んだのか」「その学びを今後どのように活かしていきたいのか」といった深い洞察を得ることで、単なる経験の羅列ではなく、ストーリー性のある魅力的な自己PRを作成することができます。
就職活動では、このような具体的で説得力のある自己アピールが、企業からの高い評価につながります。
このように、自己分析は自己PRや志望動機作成の基盤となる重要なプロセスといえます。
効果的な自己PRの作成方法については、別記事「価値観の書き方!例文を掲載!簡単に解説!!」で詳しく解説しています。
「深い自己理解があってこそ、心に響く自己PRが生まれます」
将来の目標が明確になる
自己分析を行うことで、自分が本当に目指したい将来の方向性や具体的な目標が明確になります。
なぜなら、自己分析を通じて自分の価値観、強み、興味関心を深く理解することで、それらと整合性のとれたキャリアパスや人生の目標を設定できるようになるからです。
例えば、「学生時代のボランティア活動で社会貢献に喜びを感じた」「チームでのプロジェクト運営が得意だった」といった経験の分析から、「NPO団体でのプロジェクトマネージャーを目指したい」といった具体的な将来像が見えてくることがあります。
就職活動では、このような明確な将来像を持つことで、志望する業界や企業を絞り込む際の重要な判断基準となります。
このように、自己分析は将来のキャリアプランを具体化する上で非常に効果的なツールといえます。
「自分の本質を理解することで、確かな未来が見えてきます」
まとめ
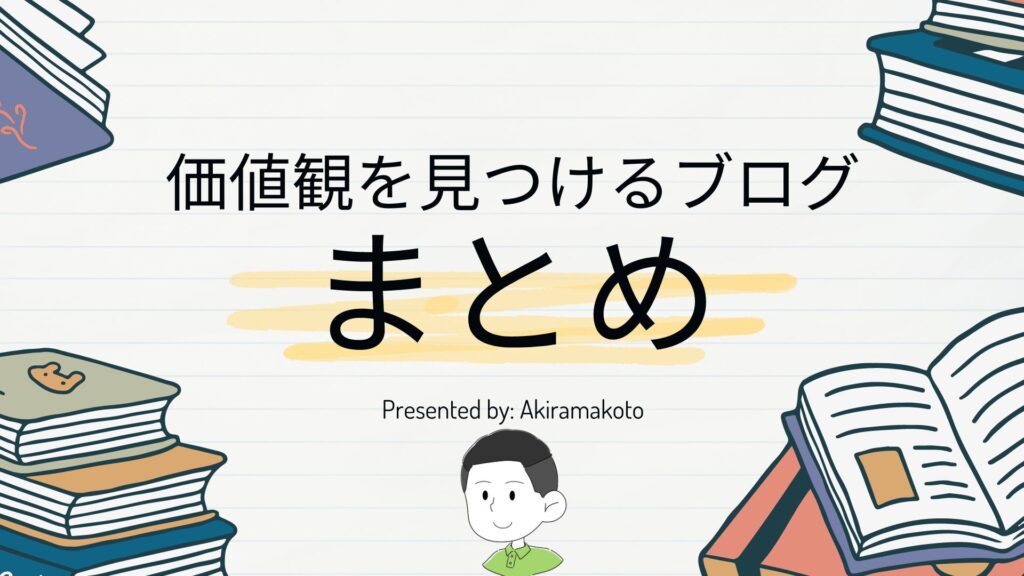
自己分析は、キャリアプランニングにおいて不可欠なプロセスです。
主な手法として、自分史の作成やモチベーショングラフの活用があり、これらを通じて自己理解を深めることができます。
自己分析の主なメリットには以下があります。
- 自分自身の価値観を明確に理解できる
- 説得力のある自己PRや志望動機の作成に活用できる
- 将来の目標設定がより具体的になる
ただし、自己分析に時間を使いすぎないよう注意が必要です。
就職活動全体のバランスを考慮しながら、継続的に自己理解を深めていくことが重要です。
効果的な自己分析を通じて、より自分らしいキャリア選択が可能となり、説得力のある就職活動につながります。









